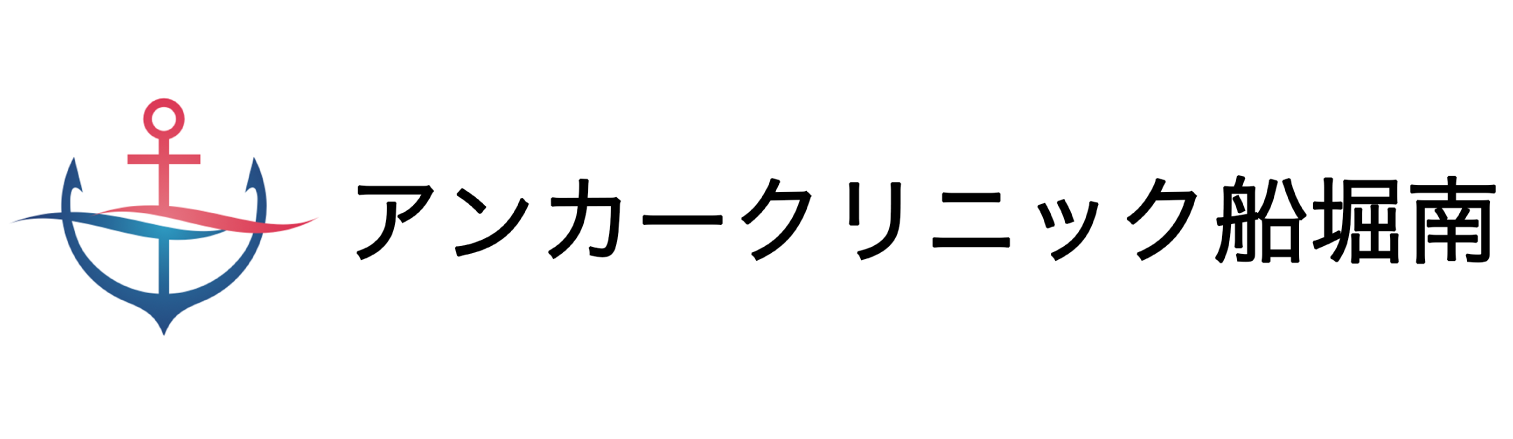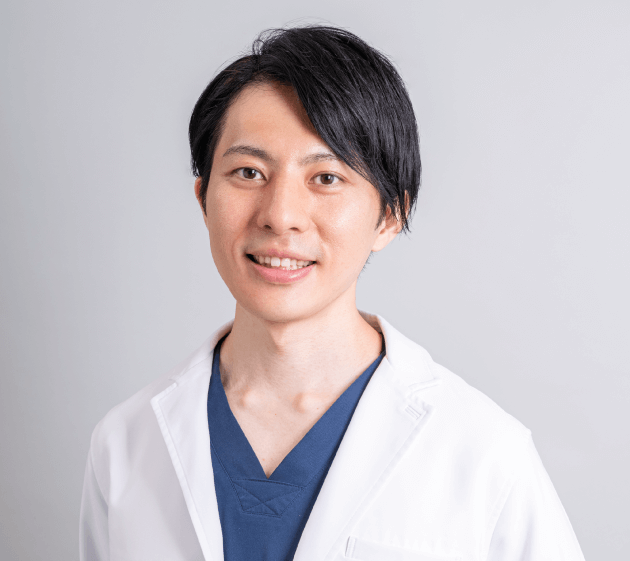この記事のまとめ
「胃もたれが続く」「胃が痛いのに検査では異常がない」「食後の膨満感がつらい」ーーこのような胃の症状を訴えて、非常に多くの方が当院にも受診されます。症状はあるのに検査をしても異常がなかった、という場合に診断される病気が、機能性ディスペプシア(FD:Functional Dyspepsia)です。 機能性ディスペプシアは、日常生活や仕事のパフォーマンスにまで影響を及ぼすことがあり、正しい診断と治療が重要です。この記事では、機能性ディスペプシアの症状・原因・診断の流れ・治療法・生活上の注意点について、江戸川区船堀にあるアンカークリニック船堀南の消化器内科専門医が、専門医の視点でできるだけわかりやすく解説します。
要約
・機能性ディスペプシアは「検査で異常がないにもかかわらず、胃痛や胃もたれ、腹満感、食後の嘔気などの症状が続く病気」。 ・消化管の運動機能異常、胃酸分泌の異常、精神的ストレスなどの複数の因子が絡まり合って症状が出ると考えられている。 ・治療には薬物療法や認知行動療法などがある。 ・食事や生活習慣の改善も治療に含まれる。 ・アラームサイン(器質的疾患を疑う症状や病歴)がある場合、治療効果が乏しい場合などには胃カメラ検査などで器質的疾患を除外する必要がある。
2. 機能性ディスペプシアとは?
・ディスペプシアとは ディスペプシア(dyspepsia)は、胃の痛み、胃もたれ、腹満感など、みぞおち(心窩部といいます)周辺に現れる不快な症状を指す医学用語です。 日本消化器病学会の「機能性消化管疾患診療ガイドライン2021」では、機能性ディスペプシアを以下のように定義しています。 「症状の原因となる器質的,全身性,代謝性疾患がないのにもかかわらず,慢性的に心窩部痛や胃もたれなどの心窩部を中心とする腹部症状を呈する疾患」 つまり、「検査で異常がないにもかかわらず、胃痛や胃もたれ、腹満感、食後の嘔気などの症状が続く病気」です。 ・胃カメラ検査で異常が見つからない 機能性ディスペプシアの患者さんには器質的疾患(がんや潰瘍などの炎症、損傷)がありませんので、胃カメラ検査を行っても症状の原因となるような異常は見つかりません。 ・慢性胃炎やピロリ菌感染との関連は? かつてディスペプシア症状に対して「慢性胃炎」という病名が使われることがありましたが、これは誤りです。慢性胃炎は胃粘膜に組織学的な炎症が起きていますので、器質的疾患に該当します。 また、ピロリ菌感染によりディスペプシア症状がもたらされていることがあり、除菌治療を行うと症状が消失、改善する人がいます。この場合は機能性ディスペプシアではなく、「H.pylori関連ディスペプシア」という別の疾患と診断されます。
機能性ディスペプシアの主な症状と日常生活やQOL(生活の質)への影響
国際的に用いられるRome基準では、機能性ディスペプシアの診断基準の中に、以下の4つの症状を挙げています。 ・食後膨満感 ・早期満腹感 ・心窩部痛 ・心窩部灼熱感 実際にはこれら以外に「空腹時の不快感」「悪心」「げっぷ」などの症状を訴える方も多いです。日本の診断基準では症状を限定せず、それがディスペプシア症状かどうかを医師が判断しています。 なお、「胸焼け」などの逆流症状は、胃食道逆流症(GERD)による食道の症状に分類され、機能性ディスペプシアの症状には含まれません。 Rome基準では「6ヶ月前から症状があり、直近3ヶ月間症状が続いていること」が診断に必要ですが、日本では診断のための罹病期間に明確な決まりはありません。これは症状の持続期間と症状の強さ・QOL(生活の質)の低下に相関がないことが研究で示されているためです。 つまり、発症して間もなくてもQOLが低下するほどの苦しい症状を呈しうるということです。
機能性ディスペプシアの原因は?
原因は一つではなく、以下のような複数の要因が関係していると考えられています ・消化管の運動機能異常 ・胃酸分泌の異常 ・遺伝的な要因 ・内臓の知覚過敏 ・精神的ストレス また、急性感染性腸炎の回復後にディスペプシア症状が続く「感染後機能性ディスペプシア」というのもあります。例えば、とある年の年末に急性腸炎が非常に流行しましたが、腸炎の下痢や発熱などが治まったあとにディスペプシア症状が長引き受診する方が多くいらっしゃいました。
検査と診断の流れ
機能性ディスペプシアの診断は、症状やその経過、既往歴などの病歴を聞き取り、診察を行って器質的疾患を除外することが基本です。診断に胃カメラ検査は必須ではありません。ただし、アラームサインがある場合には、胃カメラ検査や血液検査、腹部超音波検査、腹部CTなどの精密検査が必要です。 アラームサインとは、胃潰瘍や胆嚢炎、がんなどといった器質的疾患を疑う症状や病歴のことです。具体的には、高齢での新規症状発現、体重減少、繰り返す嘔吐や吐血、食べ物が飲み込みにくい、飲み込むとき痛みが出る、腹部腫瘤、発熱、血縁者に食道がんや胃がんがいる、などです。 アラームサインがない場合でも、初期治療に反応が悪い、症状を繰り返す、悪化する、などの経過をたどる場合は、隠れた器質的疾患がないかを念頭に追加で検査を行います。 機能性ディスペプシアの診療においては、隠れた器質的疾患を見過ごすことがないようにすることが、最も重要です。
機能性ディスペプシアの治療法
機能性ディスペプシアでは検査の異常がないため、患者さん自身が「症状が和らいだ」と実感することが治療の目標になります。
薬物療法
症状に応じて以下のような薬を使い分けます。 酸分泌抑制薬 PPI:エソメプラゾール、ランソプラゾール など H2RA:ファモチジン など PCAB:タケキャブ® 消化管運動改善薬 AChE阻害薬:アコチアミド 5-HT4作動薬:モサプリド オピオイド受容体刺激薬:トリメブチン ドパミンD2受容体拮抗薬:メトクロプラミド、ドンペリドン、イトプリド 抗不安薬: タンドスピロン 漢方薬: 六君子湯 など
認知行動療法(必要に応じて)
薬物療法で効果が乏しい場合には、心療内科的アプローチとして認知行動療法を行うことがあります。症状が出現するきっかけを患者さんが自ら分析し(認知)、どのような考え方や行動をとることが症状を改善したり、症状出現を回避することにつながるかを、治療者と一緒に考えます。必要に応じて、心療内科の専門医師の診察を受けていただきます。
ピロリ除菌療法(H.pylori関連FDの場合)
ディスペプシア症状があり、器質的疾患を想定して行った検査でピロリ菌感染が認められた場合、ピロリ菌の除菌治療を行います。除菌後に症状が改善した場合は、H.pylori関連FD(1. 機能性ディスペプシアとは?で説明しています)と診断されますが、6か月〜1年の経過観察が必要であり、実際の診療では明確な因果関係を判断するのは難しいことが多いです。
食事や生活習慣で気をつけたいポイント
機能性ディスペプシア患者には不眠の方が多く、運動不足に関連しているという報告や、機能性ディスペプシアと食事内容の関連についての報告は少ないですがあります。しかし現時点では機能性ディスペプシアと特定の食事・生活習慣との明確な関連を示すエビデンス(根拠)は十分とはいえません。しかし、エビデンスは乏しいものの不利益もないため、症状の悪化を防ぐ目的で以下のような指導が推奨されています。 ・食事は満腹まで食べず、少量を数回に分けて摂取 ・脂質の多い食事を避ける ・アルコールやカフェインの摂取を控える ・禁煙 ・適度な運動と睡眠の確保
早めの受診と適切な対処を
機能性ディスペプシアは症状で診断されるため、器質的疾患が隠れている可能性を常に念頭において我々医療者は診療にあたっています。 患者さんご自身でその症状や経過がアラームサイン(器質的疾患を疑い、検査を行うべき症状や病歴)であるかを判断するのは難しいものです。自己判断は避け、専門医へ相談することが重要です。 胃の不快感や膨満感などが続く場合は我慢せず、消化器内科を標榜している医療機関での受診をおすすめします。 当院、江戸川区船堀のアンカークリニック船堀南では、消化器内科の専門医が機能性ディスペプシアの診療を行っています。症状にお困りな方は一度ご相談下さい。